射場整備の手引き
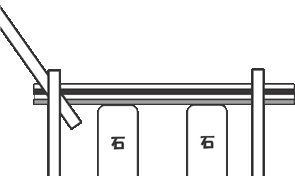
・てきとうに書かれたこの図は葎射場を横から見た場合の略図。
・縦に2本、斜めに1本入っている変な棒は射場のポールにあたる。
・石は射場を補強しているもので、ブロック等を使っている
・弓立ての角材はその辺のものでOK
・色分けされた横に渡っているものは射場の板を現している。
・色分けされているのは、上から表板、ビニルシート、土台板、枠組みとなっている。
射場整備のポイント
・表板
防腐剤を塗ってあるが、基本的に毎年交換した方が良。
どうしても予算が無い場合以外は換えていけば常に足場がきちんとした射場で引けることになるのでなるべく換えてもらいたい。
卓球台が使ってあるがそろそろ寿命なのでベニヤを購入して換えると良いかと。
・ビニルシート
現在は表が緑、裏が黒のその辺にあったものを使用。今回は特に破壊後があるため要交換。
安物でもいいので穴があいてないものを使うこと。カットしやすいものだとなお良。表板をはがした場合は釘の穴があくので、必ず補強するか換えること。
・土台板
2003は破壊されてしまったので穴のあいた所は要交換。腐ってなければ交換の必要はなし。
余裕があれば防腐剤を塗ると長持ちする。
・枠組み
こちらも防腐剤を塗っていないので塗ると射場が長持ちする。壊れているようなら木を継ぎ足すなどの補強が必要。
頑丈に作ってあるので大事に使えば相当長持ちするはず。
・枠組みの下
木が交差する所に石などを入れて落ちないよう補強してある。一応チェックしてずれがあるようなら直して欲しい。
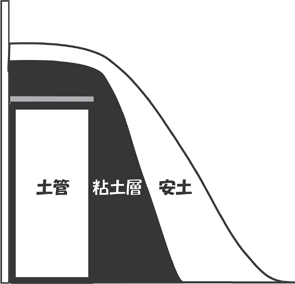
安土の中は左図のようになっていて、土管の上には中に粘土が落ちないように板を置いてある。
今現在はロッカーの蓋がかぶせてあるはず。その上に粘土層、安土という順番にかぶせてある。
これがうちの安土の状態である。
| ・通常の安土崩しと同様に安土を崩す ・安土崩しと平行して粘土層を崩す(安土崩しの中身は省略) ・崩した粘土をシートか何か、地面の土やゴミと一緒にならないように乗せる ・粘土の中のゴミを取り粘土に水を与えてひたすら練る ・硬く固まってしまっている粘土があるのでそういうのをひたすら崩し、練る ・粘土をひたすら練る |
この粘土層崩しの中で一番大変かつ単純で暇な作業が粘土を練る作業である。
粘土は長い間ほっておくと水分が飛び、石のような塊になってしまう。まさに堆積岩。
崩せないことは無いのでシャベル等武器を駆使して崩し、水を与えてほぐすという方法をとることが出来る。というよりかそれ以外の方法がない。
裸足になって踏みながら練る原始人系から、シャベルでひたすら突き進むガテン系、
座り込みスコップで手元の小さなかけらを崩す砂場遊び系など人それぞれ好きな方法でやると良い。
飽きるので自分なりの楽しみを見つけるべきだと思われる。
大きなビニルシートでないと乗せたときにゴミが入る恐れがあるが、大きすぎると中のほうの粘土が練られないまま終わってしまう可能性があるので、
程よい大きさのシートを考えて使うのが良いかも。特に、春先にやると思うが、桜の花が曲者になってくる。
舞い落ちる桜と交戦しながら粘土層を練ることに春を感じられれば一人前といえる。
この粘土を練る作業と平行して建物の方の作業を行う。
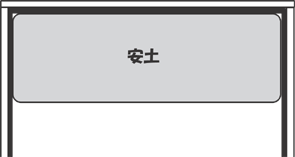
ベニヤ板に湿った粘土層や安土が触れるとあっという間に腐ってしまうので
ビニルなどで補強する必要がある。
平成14年に粘土層を崩したときには、
その準備が無かった為学校中からゴミ袋を集めて何重にも重ねて貼った、という妙 エピソードがある。
安土を崩してみると分かるが、非常にかっこ悪い。
というわけでやるときゃちゃんとビニルシートか何かを準備してからやると良。
意外にこのビニルシートを貼る作業が面倒かもしれない。
| ・一度土管をどけてビニルシート(ゴミ袋)をはがし、ベニヤ板の状態を確認 ・ベニヤがやばそうなら交換 ・少なくともベニヤは5〜6年ごとには交換【前回交換:平成14年春】 ・ベニヤを交換するなりなんなりしたら、ビニルシートを貼る ・この時外観に気を使ってみると葎がセンスアップ ・ビニルシートが貼れたら土管を戻す(シートを破らないように注意) ・土管に蓋をする |
ここまで作業が終わったら粘土の方も大体崩れて練りあがる頃のはず。終わってなかったら皆で原始人に戻って粘土を練る。
練り終わったら親の仇のように粘土を土管等に向かってひたすら投げつける。
粘土層崩しの楽しみはここに全て集約されているといっても過言ではない。投げつけるのに飽きたら台車で粘土を一気に運ぶ。
運んだ粘土をまずは土管が隠れるように、そして程よく傾斜が付くようになんとなく積み上げる。
出来上がったら安土を積み上げやすいように上辺や斜面をてきとうにならす。
粘土層崩し特有のものとしてやるべきことは大体ここまでで、後は普通の安土崩しと同じように安土を積んでいく。
きれいにならした後に安土の前で皆で記念写真を撮るるのが毎年恒例になっているが、やるも良し、やらぬも良し。
難点は皆で前に並ぶとせっかくの安土が見えなくなってしまうことくらいだ。
大体どんな雰囲気になるかが知りたければ、112回のHPで平成14年の安土崩しの様子を見ることが出来る。
【112回生の弓道部々室 online】 http://kyudo112.hp.infoseek.co.jp/